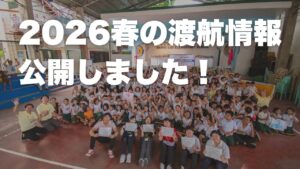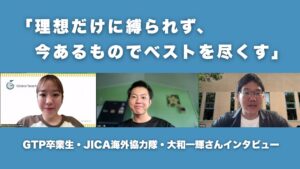GTPセブ参加者体験談 橋爪萌 大学4年生〜子どもたちの「できた」を引き出すには〜
都留文科大学教養学部学校教育学科4年生の橋爪萌です。周りの友達からは、はっしーと呼ばれることが多いです。
私は、小学校1年生の時の担任の先生の声かけをきっかけに、逆上がりができるようになりました。その時の達成感から体を動かすことが大好きになり、10年以上空手道やソフトボールに取り組んできました。この経験から、子どもたちの 「できた」を引き出したいという思いから教師という職業に憧れを抱き、教育について学ぼうと決めました。また、人間観察が趣味で、人の動きや表情から気持ちを想像する毎日を過ごしています。

1、なぜGTPへの参加を決めたのですか
私は、人と関わることが大好きであり、また自分とは違う人に興味があります。そんな私にとって、文化も食事も年齢も異なる海外の子どもたちは、「なぞ」に包まれていました。だからこそ、日本の文化とは異なる地へ足を運び、実際に子どもたちを知りたい、肌で感じたいと思ったのがきっかけです。
そんな中、GTPのインスタグラムで、「海外で教育実習をしよう」という広告が流れてきました。文化の異なる子どもたちと触れ合いたいと思っていた私にとって、とても魅力的に感じました。初めは、「詐欺ではないのか?!」と疑いましたが、実際に代表の平岡さんの教育に対する熱い思いを聞いて参加を決意しました。
2、実際に参加してみてどうでしたか?
実際に参加してみて、毎日が新しい気づきや挑戦の連続でした。私は、英語でコミュニケーションを取ることさえままならなかったので、子どもたちに英語で授業をすることに対して、とても不安を抱えていました。ですが、計3回の授業実践を通して、言語の壁を乗り越えて、子どもたちや先生方と心が通じ合えたように感じました。私にとって、忘れられない瞬間となり、私の財産です。
授業実践
私は、フィリピンの小学校で5年生の算数を担当しました。
セブ島での授業実践1回目は、私にとって本当に刺激的な経験でした。初めて異国の地で子どもたちを前に授業をするという緊張感と同時に、「だるまさんがころんだ」という日本の遊びを通して子どもたちと繋がれるという期待もありました。授業が始まると子どもたちは、私に対して興味を示してくれました。最初は、「だるまさんがころんだ」という遊びに子どもたちは戸惑いながらも徐々にルールを理解し、笑顔で楽しそうに参加してくれる姿を見て、胸がいっぱいになりました。
英語での説明や指示は完璧ではありませんでしたが、身振りやデモンストレーションを交えて伝えることで、言葉の壁を越えられる瞬間がありました。その時、「伝えよう」とする気持ちの大切さを実感しました。子どもたちから「もっとやりたい!」「もう1回やる!」と声を上げてくれた時に自分の工夫や意図がしっかり届いたのだと感じ、とても嬉しかったです。
子どもたちの笑顔を引き出せることの幸せを何よりも感じた1回目の授業実践でした。

2回目の授業実践では、算数の「分数×分数」の授業を行いました。正直、日本語で教える場合でも難しい単元を英語で分かりやすく、どのように伝えるのかという点に大きな不安を感じていました。私は、少しでも楽しく、そして体験的に学べるようにゲーム性を取り入れた授業を計画しました。子どもたちに問題を解くタイムリミットを設け、チーム一丸となり学べる活動を通して、分数の計算に対する興味や意欲や「できた」を引き出したいと考えていました。
しかし、実際に授業を行ってみると元気いっぱいのクラス全体をまとめることができず、学級コントロールの難しさを痛感しました。ゲームが盛り上がるあまりに一部の子どもたちが中心となって進んでしまい、全員をうまく巻き込むことができなかったことが悔しく、心残りです。
「楽しさ」と「学び」を両立させることの課題が明確になった2回目の授業実践でした。

3回目の授業実践では、前回の悔しさをしっかりと振り返り、「クラス全員が理解できる」をテーマに授業づくりを行いました。子どもの躓きポイントであった「分数の約分」に焦点を当てました。授業では、いきなり計算に入るのでなく、音楽に合わせながら九九の振り返りからスタートしました。子どもたちにとって馴染みのある内容から始めることで、安心感を持って参加できるように工夫しました。その後、分数をより身近に感じられるように、ピザの絵を用いて「どれぐらいの大きさを表しているのか」を視覚的に示しました。
活動中は、できるだけ多くの子どもたちに声をかけ、理解度を確認しながら進めることを意識しました。GTPにはペア制度というものがあり、私一人では子どもたちの様子や理解度を確認しきれない部分を補ってくれる存在もいてくれることで、安心して授業を進めることができました。授業の最後の理解度チェックシートでは、「よくできた!」「わかったよ!」と答えてくれた子どもたちが90%以上に達し、私自身も心から嬉しかったです。 一人ひとりの表情を見逃さず、全員の「わかった!」を引き出せる教師になりたいと強く感じた3回目の授業実践でした。

3、GTPを終えて、これからどうしていきたいですか
” 様々な実態の子どもたちと出会う!”
セブ島では、貧しさの中でも明るく前を向いて生きる子どもたちの姿を目の当たりにしました。街中では、服や靴を買うお金もなく裸足で歩き、物乞いをする子どもたちもいました。日本では、当たり前に感じていた「クーラーのある場所で勉強すること」や「食べられるものがあること」が、彼らにとっては大きな喜びであり希望であることを実感しました。その瞬間に自分の中の「当たり前」がどれほど限られたものであったのかに気づかされました。
この経験を通して、私は教師として、「子どもを受け止める力」をもっと育てたいと感じています。子どもの背景や環境がどうであれ、その子自身と向き合い、受け止めた上で、「できた」という達成感を引き出していきたいと思いました。だからこそ、今後はもっと多様な子どもたちと出会い、さまざまな経験を重ねていきたいです。
セブ島での子どもたちとの出会い、10日間という限られた時間ではありましたが、楽しい時も不安な時も共に過ごし、切磋琢磨できた仲間には本当に感謝しています。ここでの学びが、きっと私の教師人生の原点になると思います。今後は教師として日本の素晴らしさを子どもたちに伝えていきながら、JICAにも挑戦しようと考えています。